音楽のプレゼントをあなたとあなたの大切なひとへ。
-

【CD】Rêverie 日曜日の夢の始まり | 上柿絵梨子 Eriko Uegaki
¥3,850
SOLD OUT
2020/12/25 Release コロナ渦のはりつめた心を解き放ち優美な夢の世界へ誘うピアノ即興演奏 自粛中の2020年3月から毎週日曜日の夜にYoutubeにアップされた即興演奏のプロジェクト ” Rêverie 日曜日の夢の始まり ” が待望のマスタリング音源化。 穏やかで静かな夜を過ごせるよう祈って届けられた全10回にわたる即興は混沌と過ぎる不安な日々から温もりの夢の中に誘い未来の想像、希望、安らぎを生み出します。 音と共に光や優しい風、淡い原風景などをイメージしたメッセージやドローイング、写真も織り交ぜられ、 ブックデザイナー山元伸子氏(ヒロイヨミ社)によるデザイン、製本家都筑晶絵氏によって綴られた装丁でより温かみを感じられるCDブックとなっています。2020年クリスマスに届けらる上柿絵梨子からの贈り物。ボーナストラックとして2020年6月にインスタレーションで共演した”はいいろオオカミ + 花屋西別府商店” の鏡の作品からイメージされた新曲Mirror収録 。限定300部サイン入り Rêverie 日曜日の夢の始まり Rêverie op.1 Rêverie op.2 Rêverie op.3 Rêverie op.4 Rêverie op.5 Rêverie op.6 Rêverie op.7 Rêverie op.8 Rêverie op.9 Rêverie op.10 Mirror ¥3500+税 UGRK-3703 Piano, Message, Drawing,Produced : Eriko Uegaki Mastering : Katsunori Fukuoka (Flysound co. ltd) Photo : Momoka Omote Design : Yamamoto Nobuko Bookbinding : Akie Tsuzuki Eriko Uegaki / 上柿絵梨子 HP www.erikouegaki.com Instagram [erikouegaki]

-

1冊でわかるポケット教養シリーズ 1日1曲 365日のクラシック
¥1,210
内容「BOOK」データベースより 1分で身につく名曲の教養。日めくりカレンダーのように毎日、縁ある音楽と出会う。 作曲家や演奏家の誕生日や命日、名曲が初演された日、音楽に関係した出来事があった日…。 1日ごとのテーマから出会う「クラシック入門」であり「クラシック音楽史」でもある1冊。 バッハやヘンデルの時代からラフマニノフ、ショスタコーヴィチまで、およそ300年をカバー。
-

1冊でわかるポケット教養シリーズ 吉松隆の 調性で読み解くクラシック
¥1,045
長調は「楽しい」、短調は「悲しい」? 作曲家はどうやって調性を選ぶの? 調性(スケール)については不思議なことがいっぱい。これを作曲家の吉松隆氏が分かりやすく解説します! 和声法だのコード進行だのを何も知らなくても、最後の「ジャーン」という和声に辿り着くと誰でも「ああ、終わった」という解放感に満たされる。 これは「音」というものが最初から持っている「科学的」に説明できる性格なのだろうか。 あるいは、それを聞く人間の耳や感情によって起こる「感覚」の問題にすぎないのだろうか。 もしくは、人間が生まれつき持っている「本能」? それとも子供の頃から聞いてきた音楽の体験から染み込んだ「記憶」あるいは「くせ」? この書では、そんな「ハーモニー」や「調性」の謎と秘密について、独断と私見も含めて解説してゆこう。(本書「はじめに」より) ※本書は2010年9月小社より発刊された『「運命」はなぜハ短調で扉を叩くのか?~調性で読み解くクラシック~』を文庫化したものです。
-

1冊でわかるポケット教養シリーズ 形式から理解するクラシック
¥1,045
曲の仕組み、成り立ち、構成などを知っていると音楽は100倍楽しめる! 名曲のスタイルを分析し、曲の背景を知ると、音楽をもっと楽しく聴くことができます。 クラシックファン必携の1冊。 名曲80曲を使い、クラシックを「仕組み(音楽形式)」と「構成」からわかりやすく分析する。 ※本書は、2010年に小社より刊行された 『クラシックの聴き方入門~名曲のスタイル分析全80曲~』を文庫化したものです。 CONTENTS ■序章:動機(モティーフ) ■第1章: 2部形式・複合2部形式 ■第2章: 3部形式・複合3部形式 ■第3章:変奏曲形式 ■第4章:ロンド形式 ■第5章:ソナタ形式 ■第6章:ロンド・ソナタ形式 ■第7章:カノンとフーガ ■第8章:オペラ ■第9章:宗教曲 ■第10章:いろいろな曲種 ■第11章:クラシック音楽のジャンル
-

1冊でわかるポケット教養シリーズ 和声法がぐんぐん身につく本
¥1,045
複雑な和声法を、軽快な語り口調でていねいに解説。 好評の『1冊でわかるポケット教養シリーズ 和声法がさくさく理解できる本 』に続き、本書は少しのステップアップをはかれる1冊です。 ●難解とされる和声を、基礎からていねいに解説 ●「実践で理解を深めよう! 」巻末に充実の課題集付き ●気軽に読める語り口調でするする進められる 目次: 第1章 音の名前と音階 第2章 和声法の基礎 第3章 特別な和音と和音外音 第4章 数字付低音 第5章 課題実施の手引き 巻末付録 課題集/実施例 ※本書は2014年刊行『解きながら身につく 土田京子のスーパー和声法講座』(小社刊)(ISBN:9784636903003)を文庫化したものです。 ■著者について 土田 京子(つちだ・きょうこ) 東京都立駒場高校音楽科を経て、東京藝術大学作曲科卒業。 トロント王立音楽院ピアノ科卒業。 1977年から1994年まで聖徳学園短期大学(現聖徳大学)音楽科講師。 1994年から2007年まで、同志社女子大学音楽科講師。 東京・京都・大阪・福岡にて音楽研究グループ“ ティータイムトーク" を主宰。 東京・練馬にて、音楽教師の再教育塾「説き語り音楽塾」を主宰、豊かな教師力の養成に全力を挙げている。 「アカンサス音楽教育研究所」所長。 ・説き語り音楽塾 ・アカンサス音楽教育研究所
-

1冊でわかるポケット教養シリーズ 和声法がさくさく理解できる
¥1,045
「音楽をやるうえで和声は覚えておいたほうがいいけど、複雑で難しくて大変! 」 そんな声に応えた1冊が登場。著者のユーモラスでわかりやすい語り口調で和声を知ろう! ● 難解とされる和声を、基礎からていねいに解説 ● 譜例と実践練習を間に差し込むことで、理解度アップ ● 気軽に読める語り口調でするする進められる ■目次 第 1 章 音の名前と呼び方について 第 2 章 音階を作ろう 第 3 章 “和音"って、どうやって作るの? 第 4 章 自分でも書いてみよう! 合唱の「はじめの一歩」 第 5 章 「カデンツ」って何? 第 6 章 仲間を増やそうPart1ノッポの彼ら 第 7 章 メロディに和音をつける 第 8 章 「借用和音」って何? 第 9 章 仲間を増やそうPart2変わり者の彼ら 第10章 転調 第11章 「和音外音」を知っていますか? ルールブック 番外編楽曲分析・逆引き辞典 ※本書は『これだけは知っておきたい 土田京子の説き語り和声法講座 (ISBN:9784636816518 )』(2009年8月刊)を文庫化したものです
-

1冊でわかるポケット教養シリーズ 楽典がすいすい学べる本
¥1,045
大好きな音楽に近づくために、どうしても知っておいていただきたい音楽上のルール・約束ごとが「楽典」です。(中略)これまで書かれた本の奥は「独学する人」に親切ではありませんでした。そもそも、言葉が難しくて(日本語なのに! )参ってしまう。この欠点を何とか退治してみよう、というのが、この本が誕生した理由です。 (「はじめに」より) ■目次 第1章 楽譜の約束ごと 第2章 音楽の成り立ち 第3章 クラシック音楽の歴史 第4章 オーケストラのメンバーたち 第5章 楽語ものがたり ※本書は2005年刊行『改訂版 これだけは知っておきたい土田京子の説き語り楽典講座 音楽史付』(小社刊)を文庫化したものです。
-
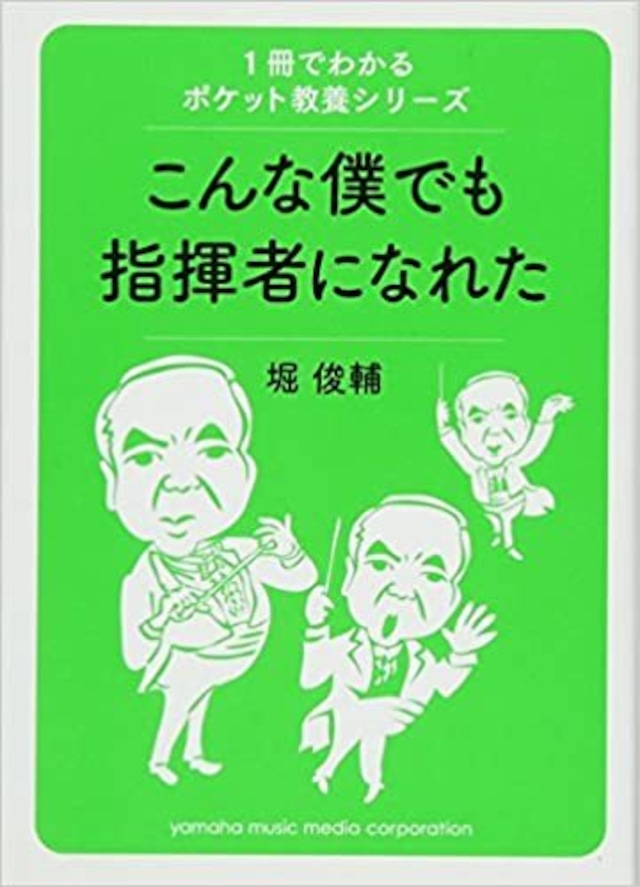
1冊でわかるポケット教養シリーズ こんな僕でも指揮者になれた
¥1,045
紆余曲折の後、40歳にして東響を振って正式デビューしたホリヤンこと堀俊輔による、抱腹絶倒のエッセイ。 あちこちのコンサートにもぐり地道な勉強を続けた貧乏学生時代、電車の発着音に音がかき消される駅ナカでのコンサート。 そんな下積み時代を経て、憧れの「題名のない音楽会」の舞台、ニューヨークへの留学、審査員として招聘された「プロコフィエフ国際コンクール」と、着実に指揮者として成長していく様子が描かれる。 故人となった朝比奈隆、黛敏郎、山本直純ほか多くの名音楽家たちとのエピソードも貴重。 ※本書は、2003年に小社より刊行された『ヘルベルト・フォン・ホリヤンの本日も満員御礼! 』を加筆・再編集し、文庫化したものです。
-

1冊でわかるポケット教養シリーズ オーケストラの世界
¥1,045
オーケストラの楽しみ方は、この1冊でわかる! 知っておきたい基礎知識からタイプ別の鑑賞方法、オーケストラを創り上げる楽員や黒子たちのインタビューまで。 オーケストラに魅了された著者が教える「本当の魅力」。
-

1冊でわかるポケット教養シリーズ ピアノが上達する音楽の思考法
¥1,045
表現力豊かにピアノを弾くためには、楽譜を「読んで」、音楽を「聴いて」、上手に「弾き」、それらを定着させるために「書く」必要があります。 本書では、この「読む」「聴く」「弾く」「書く」という4つ音楽の基礎能力を磨く方法を指南し、まず鍵盤を触る前に知っておきたい音楽との向き合い方を解説しています。 [目次] ■1章 音楽をよく読むために 第1話 楽譜と向き合う 第2話 楽譜をよく視る ■2章 音をよく聴くために 第3話 音同士の関係を理解する 第4話 メロディを大切にする 第5話 ハーモニーを味わう 第6話 リズムを感じる ■3章 ピアノを上手に弾くために 第7話 曲の仕組みを把握する 第8話 ストーリーを演出する 第9話 ピアノという楽器を知る 第10話 ピアノの表現力を身につける ■4章 書くことで総合力を高めるために 第11話 「読む」と「書く」を組み合わせる 第12話 「聴く」と「書く」を組み合わせる 第13話 「弾く」と「書く」を組み合わせる
